Robot Watch (2009/3/11)にて、第一回公開シンポジウム「次世代ロボット創出プロジェクト」の様子を紹介していただいております。
(オリジナルは、ここです。記録のために、記事内容をそのまま退避させていただくことにします。)
ーーー
3月8日、豊橋技術科学大学にて、第一回公開シンポジウム「次世代ロボット創出プロジェクト」が行なわれた。「次世代ロボット創出プロジェクト」は、平成19年度に文部科学省「ものづくり技術者育成支援事業」として採択された。学生養成を主体とした「ものづくり技術者教育プログラム」の一環として10年後に活躍するロボットの企画提案、プロトタイプつくりなどを進めている。
シンポジウムではプロジェクトリーダーの豊橋技術科学大学教授の岡田美智男氏のほか、NECの藤田義弘氏、ソニーの下村秀樹氏が特別講演を行なった。シンポジウム終了後にはロボット展示とデモンストレーションも実施された。
はじめに、豊橋技術科学大学 知識情報工学系 系長の堀川順生氏が壇上に立った。このプロジェクトには単にものを作るだけではなく「真に新しいものを作り出すことのできる人材を育成する」という意味が込められており、大学間、大学と高専、大学と企業の連携のほか、地域・世代間の協働ができるように異なるバックグラウンドを持つ学生同士、企業と学生などが連携する場を作り、学生たちの成長を促しているという。堀川氏は「好奇心に満ちた、わくわくするプロジェクトになれば、このプロジェクトは成功に近づく」と挨拶した。
続けてプロジェクトリーダーの豊橋技術科学大学 教授の岡田美智男氏が「「次世代ロボット創出プロジェクト」の目指すもの」と題して、プロジェクトの趣旨について講演した。1) 革新的な教育プログラムの開発と実践、2) 次代のイノベーション創出を担う高度IT技術者の育成、3) 既成概念にとらわれない新たなタイプのロボットあるいはメディアを生み出していくことが、このプロジェクトの目標だという。
 |
 |
| 豊橋技術科学大学 知識情報工学系 系長 堀川順生氏 | 豊橋技術科学大学 教授 岡田美智男氏 |
次世代ロボットは、まだ具体的にこれというものがないため、正解がない。だから新たなアイデアを引き出す「余地」を持っているという。また教育リソースとしてロボットは優れているという。ユーザ中心手法を学べる優れた素材であり、一人では作れないためコラボレーションが必要となる、そして実体を持っているため、ものづくりにおける身体性を回復させられるものだからだ。ロボットはさまざまな技術の集大成なので、大規模ソフトウェア作成の演習課題としても面白い対象である。豊橋技術科学大学には「天才技術者の卵」やロボコン経験者も多い。だからこれらを一まとめにする教育プログラムがあれば面白いことができるのではないか――。ATRから豊橋技術科学大学に移って2年の岡田教授はこう考えたのだという。
「新たなものは多様な価値観のせめぎあいから生み出される」、そのため、大学をまたぐ教育プログラムが必要だと岡田教授は強調した。ロボットを構成する要素技術は多岐にわたるが、各要素技術は最近はやりやすくなってきたという。
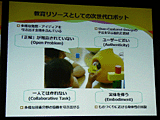 |
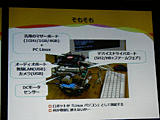 |
| 教育リソースとしてのロボット | ロボットの基本構成 |
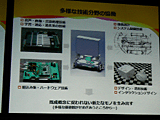 |
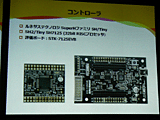 |
| ロボット作成にはさまざまな技術が必要 | コントローラには主にルネサスのSH2/Tiny SH7125を使用 |
岡田教授らのロボット作りは、一般に行なわれている機能を継ぎ足す「足し算」的やり方に対して、さまざまな部分をそぎ落とす「引き算」、そして関係性を引き出すことで本質を探るような独特のデザインアプローチで知られている。弱さを武器に他人に助けてもらうゴミ箱ロボットや、ちょっとしたものをスマート化して関係性の構築しようとしたオブジェクトなどの研究がその代表例だ。
「次世代ロボット」の創出は既成概念に囚われないことが重要である。それは単にロボットを作ることではなく10年後の私たちの生活をデザインすることである。面白いものを作るためには柔軟な発想や企画立案力が重要であり、事業規模も関係ない。小規模なチームからも面白いものは生まれ得る。問題は、どうやってそのような豊かな土壌をはぐくむか、だ。
「ものづくり」においては、いったん、答えが用意されていたり、練習問題がたくさん用意されている学校教育を「かっこにくくる」ことが重要だという。学校教育では試験は一人で受けるが、実際のものづくり現場ではむしろ組織知を活かせることのほうが重要だ。正解もなく答えはオリジナルでなければならない。練習問題ではなく本物が重要だし、教室もいらない。
そのような考えを実現するために、異分野・異年齢集団でクラスを構成し、まったく違う課題に取り組み、それを統合化する、知識・技術の分散化、オリジナルであることへのこだわり、社会的実践としての本物作り、教えながら学ぶこと、デモすること、アイディアを世の中に着地させて直の評価を受けることなどを、この教育プログラムでは実践しようとしているという。
来年4月からは、学科をまたいで参加できる「プロジェクト総合演習」という科目をもうける。「社会的実践への参加」をキーワードとした「学習環境のデザイン」を行ない、新たな教育プログラムを実施し、結果として、スーパークリエイター、マイスターを生み出すことを狙いとしているという。プログラムの対象者はおおよそ30人弱程度になる。
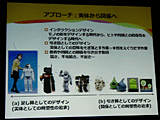 |
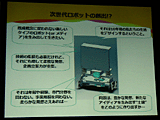 |
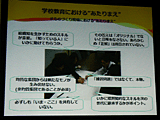 |
| 足し算デザインと引き算デザイン | 次世代ロボットデザインとは10年後の生活をデザインすること | 「学校教育でのあたりまえ」と「ものづくり現場でのあたりまえ」は異なる |
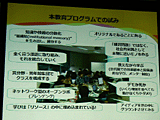 |
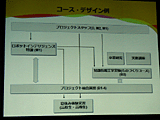 |
| オリジナルであることにこだわり異分野・異年齢でクラスを構成 | コースの例。おおよそ30名弱が受講 |
● 特別講演 NEC藤田氏とソニー下村氏が語るロボットづくりとは
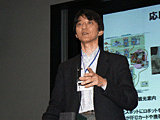 |
| NEC企業ソリューション企画本部シニアマネージャー 藤田義弘氏 |
このあとNECの藤田氏とソニー下村氏の二人が特別講演を行なった。なお両氏とも今回の講演は、あくまで学生達に、これまでに自分たちが行なってきた「ものづくり」の一部を伝えることが主目的である。本記事でも両氏の講演については簡単に内容をご紹介するに留める。講演後の質疑応答では大学教員からの質問もあったが、学生たちから積極的な質問がどんどん出て、両氏ともそれらに笑顔で真摯に答えていた姿が印象的だった。
NEC企業ソリューション企画本部シニアマネージャー藤田義弘氏は「パーソナルロボットPaPeRo の研究開発・応用開拓活動のご紹介」と題して、1997年から氏らが開発を続けている「PaPeRo」の技術開発について過程を含めて解説した。
PaPeRoはコミュニケーションを用途としたロボットである。コミュニケーションをアプリケーションとした理由は、作業をさせようと思ったらそれぞれ独自のメカや能力が必要となるが、アミューズメントや子どもの遊び相手といった用途であれば汎用コミュニケーションロボットで広くカバーできるのではないかと考えてたためだという。企業が製品開発して商品化することを考えた場合、特化した用途の専用ロボットよりも、さまざまな汎用ロボットのほうが適していると考えているそうだ。
汎用コミュニケーションロボットとは、要は未来のコンピュータ端末である。将来的には現状のようなGUIではなくロボット・ユーザーインターフェイスとでもいうべきものができるのではないかと考えているという。つまりロボットとはユーザーインターフェイスの一形態であるということだ。いずれはそうなるだろうという。それは、現状のUIがマイナスを減らすものであるのに対し、プラスを増やすものとなり、やむを得ず使うのではなく使いたいから使うようなものになることが目標だ。
ただし、20~30年後のイメージはできるが、数年後にどうやって世の中に出て行くのかとなると、難しい課題があるのが現状だ。現在の技術レベルでも役に立つ領域はあるが、技術的課題もまだ多いし、ビジネス方面の課題も少なくない。
 |
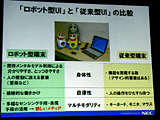 |
| いずれはロボット型ユーザーインターフェイスへ | ロボットUIと従来型UIの比較 |
NECで、画像処理・音声情報処理の研究者たちを中心にロボット開発が始まったのは1997年。最初は人の調査・観察から始まり、さまざまなデザイン案を検討した。デザイン決定後は、ロボットのキャラクター設定である。ロボットは何をするのかということだ。こうして2001年に「PaPeRo(Partner-type Personal Robot)」が登場した。これまでにおおよそ200台程度製作し、さまざまな実験を行なってきた。もともと音声処理や画像処理の研究者たちが開発してきたため、今でも顔認識などの画像処理技術や音声認識関連を得意としているロボットだ。背景音が大きいときでも認識できるノイズキャンセラや自分がしゃべっているときに人がしゃべっても認識するエコーキャンセラなどにょり、現在ではたとえばテレビをつけっぱなしの部屋であっても人間の声を正しく認識することができるという。
PaPeRoは現場での実験を繰り返すことで技術レベルも上昇している。それは単に一つの技術の向上だけによってもたらされているのではなく、PaPeRo全体の機能を向上させることで実現している。たとえば逆光で顔が隠れて見えないときは、ロボットのほうからそれを告げる。見えにくかったら近づく、角度を変えてもらうように人に頼むといった具合だ。ロボット自身が状況を判断し、自分自身のボディにフィードバックさせる。やりとりしている間に人のほうもPaPeRoの使い方を覚えていく。開発初期の頃は、モニターに一週間貸し出したところ一言も認識できなかったこともあったそうだが、いまではそういった「状況検知フィードバック」能力によって認識失敗は大幅に減ったという。
ソフトウェアに関しても力が入れられている。PaPeRoは研究者・開発者が開発した基本モジュールの上で複数のスクリプトが走ることで動作している。スクリプトそのものは行動エディターを使うことでアプリケーション開発デザイナーが簡単に書けるようなものになっている。基本モジュールはどれも部品化されており、アプリケーションに応じてそれを組み合わせることで必要機能を実現している。さまざまな技術者やデザイナーがコラボレーションしやすいようになっているのだ。
一環した動きは行動制御モデルによって行なう。スクリプトでアプリケーションは書くのだが、好き勝手に書くのは無駄なので、ノウハウとして蓄積したものは部品化していくようにし、履歴にもとづいて、ある程度たまった時点で「履歴モジュール」を作って部品化し、それを参照するようにしているという。
丸みを帯びた形状のPaPeRoだが子どもと接することがアプリケーションの一つであるため安全性に対する配慮もされており、おもちゃや電子機器の国際規格に準拠したものとなっている。
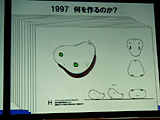 |
 |
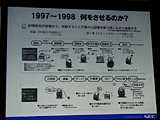 |
| 初期デザインの一例。既存のものとは違うデザインを探索した | その中からコミュニケーションしやすいデザインを見出していった | R100のキャラクタ設定検討例 |
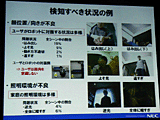 |
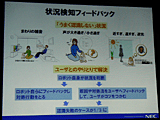 |
| 家庭用ロボットが認識すべき環境状況 | 状況検知フィードバック |
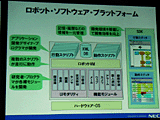 |
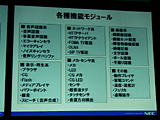 |
| PaPeRoのアプリケーションはスクリプトで書かれている | 開発してきた機能モジュール |
PaPeRoはモジュール化されたソフトウェアを使って簡単にさまざまなアプリケーションを組むことができる。また、人文系の大学との共同研究を行なっていることで知られている。ロボットとは人間に対してどういう存在なのか、ロボットが家庭や社会に出てきたときにどんな影響をもたらすのか、社会学・心理学的な影響も含めて調べるためだ。
以前は幼稚園でPaPeRoの実験を行なっても先生から邪魔者扱いされてしまうことがあったが、最近は歓迎されており父兄のなかには自分でコンテンツを作りたいという人もいるほどだという。また万博の実証実験を踏まえて、子どもたちがPaPeRoの何が気に入っているのか、PaPeRoを気に入る子どもたちに共通点があるのか、神戸大学と共同で追跡調査を行なっているところだという。
また美術系の大学とのコラボレーションや、お笑い芸人とのコラボレーションも行なっている。藤田氏はお笑い芸人「ぜんじろう」氏とPaPeRoとの漫才の様子をビデオで示した。会場ではかなり受けていた。最近は英語版の台本も充実してきているそうだ。
汎用コミュニケーションロボットとして世の中に実際に出していけるかどうかは、買ってもらえるかどうか、役に立つと判断されるかどうか、そのようなことを総合的に鑑みたプランが描けるかどうかにかかっている。今後、実証実験をしながら技術を高めていき、どこかで技術と価格がマッチして出していけると考えているという。
そのほか、将来的には今のPaPeRoを動かしているプロセッサが数千円のワンチップ化すると考えられることから、PaPeRo的ロボットインターフェイスを簡単にさまざまな端末機器に入れることができるようになると考えられる。そうなってくると、たとえば家庭用のロボットを核としつつ、モバイルでも街角端末でも車でも、どの端末を使っても自分のことを分かっている馴染みのエージェント的存在としてのPaPeRoというのも考えられる。今後もさまざまな応用展開を考えていくという。ただ藤田氏自身としてはロボットとは「インタラクションできる実体」のことだと考えており、実際にさわれる実体の距離感をいかしていきたいと考えているそうだ。
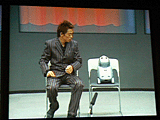 |
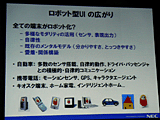 |
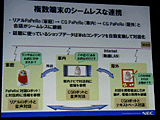 |
| ぱぺじろう。お笑い芸人ぜんじろう氏とのコラボ | 今後はロボット型UIが広がる | リアルPaPeRoとソフトウェアエージェントPaPeRoのシームレス連携 |
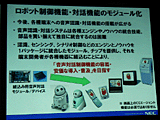 |
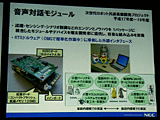 |
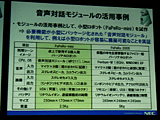 |
| ロボット制御機能のモジュール化→各種機器への組み込み | 小型音声対話モジュールを使って「PaPeRo mini」を作成 | 「PaPeRo mini」の使用イメージ |
 |
| ソニー株式会社情報技術研究所 知的システム研究部 ID研究グループ 統括課長、シニアリサーチャー 下村秀樹氏 |
次にソニー株式会社情報技術研究所 知的システム研究部 ID研究グループ 統括課長、シニアリサーチャーの下村秀樹氏が「ロボットの知能をつくる ~QRIOの開発からインテリジェンス・ダイナミクスへ~」と題して講演を行なった。「あくまで過去に行なっていた研究」だが、研究教育に貢献ができれば、と今回の講演を行なったという。なお現在の下村氏は、ロボットにはまったくさわっていないが、「インテリジェンス・ダイナミクス」に関する研究をシミュレーションベースで続けているそうだ。
人はロボットを見たときに、どのように振舞ってほしいか、という期待を持つ。たとえば人間の補助をしてほしいとか、助けてくれるとか、機械とのインターフェイスになってほしいとか、パートナーとしての存在であるとか。いずれも自らの生活を豊かにしたい、心を豊かにしたいという欲求がその根底にあるという。だが、その要求を満たすためには高度に知的な能力が求められる。たとえば新聞をとってくる、ただそれだけのロボットを作ろうとしても、いくつもの技術課題を乗り越えなければならない。それらを一つずつ乗り越えなければ、人間が欲しいロボットはできない。
つまり現状の技術では容易ではないレベルのへの期待がある。もちろん研究者はそれを実現したいと考える。だがその課題は遠い。ソニーの人間のパートナーとなってある程度勝手に動き、時間に応じて機能変化、つまり成長していくような機能を持たせた「AIBO」は15万台売れた。つまり一定の範囲では受け入れられたと考えられる。だが人間が求める機能全部を満たすのは現時点の知的機能では不可能である。だからAIBOは一つの商品例だった。
そしてQRIOである。既にQRIOが表舞台に現れなくなって数年経つためか、会場の学生たちにはQRIOを知らない人たちもいた。QRIOは実時間歩行動作パターン制御技術を持ち、高い運動性能を持っていた。ステレオカメラを使った障害物検出・測距技術、音源方向検出技術による実時間空間知覚技術、マルチモーダルインタラクション技術、個人検出・識別技術などを持っていた。
機能単体ができたら、それをどのように統合するかが問題になってくる。単調な行動ではなく記憶をベースに自分の行動を変化させる行動制御技術が必要だ。どういう状況で行動を選ぶか。そのための選択モジュールが必要になる。QRIOは内部状態に応じて、どの外部刺激を取れば「快」になるか、それに応じて行動を選択するようなビヘイビア・ベースド・アーキテクチャを持っていた。たとえば、運動欲求が高いときにボールが見えたらサッカーをするといった具合である。
またフレキシブルに状況を切り替えることもできた。たとえばボールを見て蹴ろうとしているときに一度人にトラップされたあとに、また元の行動に戻るといった動きが可能だった。言葉にすると簡単だが、絶えず変化する実環境で動くロボットで実現するのはなかなか難しい機能である。
QRIOの開発は、もちろんもう終わっている。だが認識的機能、統合的機能は、その時点で世界でも有数のレベルにあったという。だが当時、アプリケーション開発リーダーだった下村氏は、「このやり方ではやってられない」と思い始めたという。なぜならこのやり方ではいくらロボットが知的に見えるといっても、それは人間が頑張った分でしかないからだ。ロボットをより知的にしようとおもったら、人間はいつまでも付き合わなければならなくなる。
そもそも知的に見えるほど作りこみできるのかも疑問である。ある機能を機械に実現させるときには、その機能を明確に定義できればならない。だが機能を定義できない未知の領域は限りなく広がる。実世界は未知状況ばかりだからだ。イタチごっこを何とかしなければならない。そう感じながら日々もんもんとしていたという。そして、これまでとは違う知能の実現を目指す方向に進む決心をした。未知環境でのロバストネスの向上、人間が飽きない知能の実現である。
要は、問題が起きたら、その場で学習させる、実世界で学習させることが重要なのだ。そこで立ち上がったのが「インテリジェンス・ダイナミクス」である。このときにロボティクスという言葉を使わなかった理由は、神経科学や認知科学の知見をもっと偏見なく取り入れることを目指したからだったという。また、アプリケーションとして、ロボットも意識はしていたけれど、機械と人間が長期的に付き合うためにはこれまでとは質の違った知能がいずれにしても必要だと考えていたからだという。
ソニー・インテリジェンス・ダイナミクス研の成果に関しては、PC Watchでレポートしているのでそちらをご覧頂きたい。また、書籍も刊行されている。第3巻は今年中に刊行される予定とのことだ。
□ソニー・インテリジェンス・ダイナミクス2006レポート(PC)
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0427/kyokai47.htm
□ソニー・インテリジェンス・ダイナミクス2005レポート(PC)
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/0422/kyokai35.htm
□ソニー・インテリジェント・ダイナミクス2004(PC)
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0414/kyokai24.htm
以上が3年前の研究成果で、その後、ロボットを使った研究はストップしているという。ソニーは2006年1月にロボット事業から撤退することを発表し、さらにその後、ソニー・インテリジェンス・ダイナミクス研究所株式会社も2006年7月20日に活動停止した。いずれにしても人間がデータを与えてオフラインで学習している間はダメであり、基本的にはオンラインで自分で教えられなくても学習するようにしなければならない、そしてまだまだ規模が足らないと考えているそうだ。「数十年単位で見ないと評価が分からない研究だが、それでは会社はシビアなのでなかなか続かない。そのなかでも意義のある研究を続けていきたい」と語り、学生たちにロングスパンでの視座を持った研究を呼びかけた。
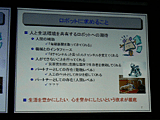 |
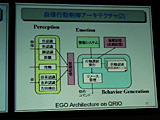 |
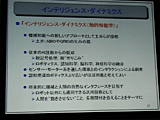 |
| 人がロボットに求めること | QRIOの行動制御アーキテクチャ | 脱作り込みを目指してインテリジェンス・ダイナミクスへ |
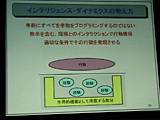 |
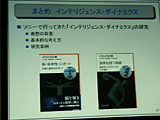 |
| インテリジェンス・ダイナミクスの考え方。経験をベースに汎化させる | シュプリンガーから書籍も刊行されており、今年に第3巻が刊行予定とのこと |
● 平成19年度「次世代ロボット創出プロジェクト」成果報告 みかんロボットやゴミ箱ロボットなど
このあと、平成19年度「次世代ロボット創出プロジェクト」の成果報告が行なわれた。それぞれチームを作って半年~1年間のロボット製作を行なったもので、それのリーダー的立場を務めた学生が発表を行なった。発表後に行なわれたデモの様子も交えてレポートする。
 |
| 豊橋技術科学大学大学院知識情報工学専攻 吉池佑太氏 |
・Sociable PC
「Sociable PC」とは豆腐のような白い箱型ロボットである。何かに合わせて体の位置を変えたり姿勢を変えることで、ある程度の志向性を示すことはできるが、それ以外は特に何もしない。センサーは加速度センサーと距離センサーを使っている。
次世代ロボットとはシンプルなデザインで、同じものに人と機械が注目するような「並ぶ関係」がキーワードになるのではないかと考えて作られたロボットだという。豆腐のような外見にしたのは、見た目としての情報を限りなくそぎ落とし、どう動いても意味が曖昧で何をしているのか分からないような存在とすることで、曖昧な動きそのものをオリジナルの意味にすることができるのではないかと考えたこと、そして距離感があまり近すぎると疲れるからだそうだ。
アプリケーションは、たとえば一緒に音楽を聞いているようなシチュエーションを考え、人の動きに少し合わせた動きをしたり、あるいはマウスカーソルにあわせて体を動かしたりするような動きをさせることで「リズムや間の共有の実現」を考えているそうだ。学生からは「いい経験になったし今後に繋がる」、また「プロジェクトに参加して自分たちが主体を持ってものを作っていくのが非常に新鮮だった」という意見ががあったという。またリーダーとなった学生にとっても、マネージメント能力が問われたという。
 |
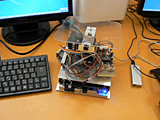 |
| 【動画】Sociable PC。表面はウレタンゴムで柔らかい | 【動画】その中身 |
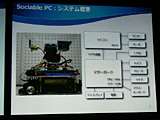 |
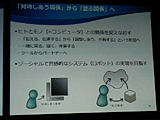 |
| システム概要 | 対峙する関係から「並ぶ関係」を目指した機械 |
 |
| 豊橋技術科学大学大学院知識情報工学専攻 竹井英行氏 |
・Sociable Dining Table
「Sociable Dining Table」は、天井に照明とUSBカメラ、4チャンネルのマイクを持ったテーブルだ。ノックするとマイクが音を拾って、机上の物体が寄ってきたりする。家族間のコミュニケーションの場でもある食卓を舞台にしたインタラクションデザイン作品だ。動き回るポットそのほかは、ダイニングテーブルに知的な存在が居たらさらに団欒の場が盛り上がるのではないかと考えて作ったという。
人は社会的な関係の中に支えられている存在である。お互いの社会的関係を調整しあうことに意味や新しい価値があるのではないか、というのが基本的考え方で、動き回るポットも、役には立たないが、いないとさびしいと感じるとなんだか面白いのではないか、それが人との関係とか人工物と人工物の関係のなかで意味を顕在化させるのだという。
 |
 |
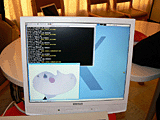 |
| 【動画】Sociable Dining Table。テーブル上の物体がゆるゆると動く | テーブル上の照明とカメラ | テーブル上の物体認識の様子 |
・蒲郡みかんロボットプロジェクト
蒲郡みかんロボットプロジェクトは、蒲郡商工会議所と豊橋技術科学大学との共同プロジェクトである。平成17年度に蒲郡商工会議所が設立した「癒しとアンチエイジングの郷がまごおり推進事業」の一環として、豊橋技術科学大学・愛知工科大学などのノウハウと蒲郡の中小企業が連携してロボット作りに取り組みことになったものだという。中小企業庁の「07年度地域資源∞全国展開プロジェクト」にも採択されている。学部3年生3人と合計4人で現在、プロトタイプを製作中だ。
温泉街でお客さんを和ませたり、見知らぬ人同士を結びつける、和み系ソーシャル・ロボットとすることを目指しているそうで、「みかんを通して人と知り合い」「蒲郡のご当地キャラで終わらせない」ような存在とすることが目標だという。
実際のロボットは旅館等に置いてお客さんを三河弁などでもてなすものとして用いられる予定で、いまはもてなしの心はどこから実現できるのかなどを調査中とのことだ。また、ちゃんと会話できるように、アイコンタクトがちゃんとできるようにしようとしているという。なおロボットは、少しだけ動くこともできるそうだ。他学科からの参加人数が増えると、プロジェクトはもっと面白くなるのではないかと考えているという。
 |
 |
 |
| みかんロボット。まだ製作途中 | 外装は完成時にはやわらかい素材にする予定だという | みかんロボットの中身。中身は2種類検討されている |
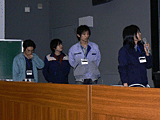 |
| 4人で発表する上野祐樹氏、菊池圭恵氏、木本誠二氏、宮崎優氏 |
・マンチカンモジュールロボット
マンチカンという短足でよたよたと愛らしい動作で歩く猫がいる。それと同じような動きでよたよたとロボットを歩かせることができれば、かわいいロボットになるのではないかと考えて、一部ロボコンでもよく使われているヘッケンリンク機構を使った「よたよた歩き機構」を作って、二つのロボットが製作された。「Be-Go」と「Gomibako」である。
「Be-Go」は、食パンのような物体が歩き回るだけのロボットである。大学のマスコット的存在となることを目指し、外観はやはりできるだけシンプルなものにして、ものから足が生えただけのようなデザインを目指したという。大きさはB5サイズのノートくらいで、そこから名前も「Be-Go」になった。まだ製作中で当日は歩かなかった。
「Gomibako」は名前のとおりのゴミ箱ロボットである。ゴミを見つけても腕がないので拾ったりすることはできないが、そこで立ち止まり、見上げたりすることで、周囲の人にゴミを拾わせるロボットである。
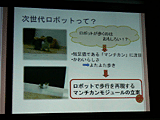 |
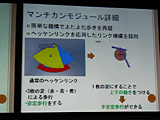 |
 |
| マンチカンという猫からヨタヨタ歩きを発想 | ヘッケンリンクを使ったヨタヨタ歩き機構 | 「Be-Go」 |
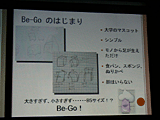 |
 |
 |
| 「Be-Go」コンセプト | Gomibakoの中身 | 【動画】Gomibakoの動き。ごとごとと歩く |
・オブジェクトを介した会話モデル
「オブジェクトを介した会話モデル」は岡田教授がATR時代に開発した「Muu」を使った研究で、ロボットが音声認識・画像認識を使って、人間が行なう積み木を評価することでコミュニケーションするもの。
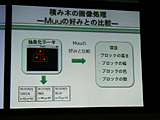 |
 |
| 積み木の画像処理を行なう | 「Muu」が積み木を見つめて評価中。このときは「まあまあ」との評価 |
そのほかのロボット研究展示も写真で簡単に紹介する。
「Mawari:」は、小さなコミュニティへの参加の場=ソーシャルインターフェイスを構成するインタラクションデバイスとして作られたロボット。USBでPCとつながり、うなづきやタッチに対して反応したりするほかRSSを集めてきて音声合成でしゃべる。「Wrigglet」は相互模倣や遅延模倣による「リズムの共有」を通じて人と原初的なコミュニケーションを行なうロボット。
「TableTalkPlus」は、会話による音声に反応して、小さなクリーチャーが寄り集まることで、会話の場を表現したインタラクションデザイン。
京都造形芸術大学との「いきものデザイン研究プロジェクト」もMuuを使った研究で、周囲を取り囲むものとの関係から生まれる「生き物らしさ」をデザインすることを目指している。自閉症児との関わりの臨床研究なども行なっているという。
「インタラクション2008」記事でもレポートしている「Sociable Trash Box」も展示されていた。またそのほか、文書要約や、コンピュータビジョン、音声エージェント、脳波コントロール・インターフェイスなど各種関連技術のポスター発表も行なわれた。
 |
 |
| インタラクションデバイスロボット「Mawari:」 | リズムでコミュニケーションする「Wrigglet」 |
 |
 |
| 【動画】Dynamixelのスマートセンサやモーターを使っている | 【動画】ぶるぶると動く |
 |
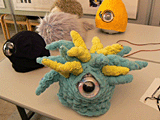 |
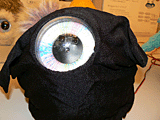 |
| 「いきものデザイン研究プロジェクト」 | 【動画】ごそごそと動く様子 | 自閉症児との臨床研究も行なっているそうだ |
 |
 |
 |
| 【動画】「TableTalkPlus」。音に反応して寄ってくる | Sociable Trash Box | 文書要約やコンピュータビジョン、脳波コントロールなどのポスターも |
■URL
豊橋技術科学大学
http://www.tut.ac.jp/
( 森山和道 ) 2008/03/11 21:24
